施光久恒『英語化は愚民化:日本の国力が地に落ちる』(集英社 2015年)の要点のまとめと考察する記事です。
今までは第一章:
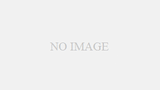
施光久恒『英語化は愚民化:日本の国力が地に落ちる』第1章から見る日本の政治の軽薄さ
施光久恒『英語化は愚民化:日本の国力が地に落ちる』(集英社 2015年)第1章をまとめながら、考察しました。日本の英語教育は本来あるべき「学術」でなく「社会」の要望に毒されています。ここでいう社会は聞こえが良いですが、「財界」の要望です。
第二章:
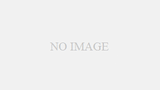
施光久恒『英語化は愚民化』第2章:ラテン語とグローバル化の失敗
施光久恒『英語化は愚民化:日本の国力が地に落ちる』第2章では、一握りの知識人がラテン語を使用し、一般人はそれ以外の日曜語を使っていた様子が説明されています。日本が英語化すると、進歩せず、600年前の中世ヨーロッパに逆戻りすることがわかります。
第三章
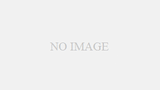
施光久恒『英語化は愚民化』第3章:明治時代に答えはあった
施光久恒『英語化は愚民化:日本の国力が地に落ちる』第3章では、日本の明治時代のグローバル化の流れとその反対する著名人たちの攻防が良くわかります。今とほとんど同じような状況ですが、明治時代の方が、西洋の知識はなかったので、焦燥感が伝わります。
と続けてきましたが、ここでは第四章の要点まとめと考察をします。
第4章 グローバル化・英語化は民主的なのか
EUで上がる疑問の声
- 地域の統合を成し遂げ一見「進んだ」ととらえられがちのEU
- 実際は大きな疑問の声
↓続く…
民主主義の機能不全をもたらしたブリュッセル体制
- EUを形成する「ブリュッセル体制」=「ヨーロッパの政治エリート同士の談合による寡占(かせん:少数がその場を支配すること)を表現したもの
- フランスの歴史人口学者エマニュエル・トッドのEU批判
- 不人気な政策(自由化・民営化)を「EUで決まったことだから」とする
- ↑自国内で十分に議論しない=「土着」でない=民主的でない
- 言語の問題
グローバル言語が損なう民主的正統性
- カナダの政治学者ウィル・キムリッカが言語の観点から批判
- デンマーク:ヨーロッパの言語上の小国
- イタリア人との議論は難しい
- でもヨーロッパを一つにしようとする…
- 民主主義になってない
- 議論に参加できるのは英語ができるエリート
「ネイション」に根差した自由民主主義
- 「進歩」と思っていたことが「分断」
- ↑を懸念し出てきた「リベラル・ナショナリズム」
- 1990年代前半に登場
- イギリス:ディヴィッド・ミラー
- イスラエル:ヤエル・タミール
- カナダ:キムリッカ
- ↑を翻訳『ナショナリズムの政治学―規範理論への誘い』(ナカニシヤ出版、2009年)
リンク
- グローバル化・ボーダーレス化は、あらゆる面で問題一般人の基本的な権利が奪われる
民主主義の前提条件としての連帯意識
- 民主政治の必要条件:連帯(仲間)意識
- 言語の共有:古くからの政治学の分野で指摘
- 19世紀イギリス社会思想家J.S. ミル『代議制統治論』
- 言語の共有:古くからの政治学の分野で指摘
- 専制政治:政治権力が人々をまとめ、秩序を作る
- 議論の根底に必要なもの:連帯意識・信頼感
- ベルギーの事例
- 北部:フラマン語(オランダ語の方言
- 南部:ワロン後(フランス語の方言)
- 東部:ドイツ語
- 1830年の建国
- 言葉を使う者同士で対立が深まる
- 1993年に新憲法:それぞれが行政機関と議会を持つ
- 問題:総選挙の度に国政が停滞
- 理由:国に「連帯感」がない
- 人類学者ベネディクト・アンダーソンの指摘
- 出版・マスコミの発達:国民意識を形成
- 共通の言語でニュースを見る
- 小説を読む
- ↑が同じ「共同体」に所属、と感じさせる
日常の言葉で政治を論じることの大切さ
- 法務省が2015年1月からヘイトスピーチを防止する啓発活動
- 「ヘイトスピーチ」を英語のまま使用
- 多くの日本語使用者は思考停止(意味が分からない)
- 何が不当かがわからないまま使用され続ける
言語の分断が格差を生み出す
- ラテン語で分断した社会を作った中世ヨーロッパ
- ヨーロッパの植民地になった経験のあるアジア・アフリカ
- 言語政策専門山本忠行の調査
- ガーナ・アフリカ諸国の経済格差=教育格差=英語・フランス語の運用能力
- 言語ができない=教育できない=社会的・経済的「不」平等が生じる
福祉政策にも連帯意識が必要
- フランスの歴史経済学者トマス・ピケティ『21世紀の資本』
- 資産課税を強化
- 税で再分配
- ↑で格差が拡大する資本主義を継続できる
- やはり「連帯意識」が必要
- 言語が異なる「連帯感」のない社会では再分配は難しい(同意が得られない)
- インドでは分断
自由そのものも言語が基礎に
- 自由とは
- 選択肢のある人生
- 具体的に言うと、職業選択
- ↑を平等に
- 母語で学べる環境がないと学べない→「選択」できない→「自由」がない
グローバル化が自由民主主義を破壊する
- 第4章のまとめ
- 母語は超大切
- 母語がないと「自由」「平等」も成り立たない
- EU批判の根本は↑。「自分たちの言葉で政治参加できない」
- それでもエリート層は言う
- 「自由! 平等! 民主主義!」
- ↑グローバル化・ボーダーレス化で中世に逆戻り…
- ↑で格差拡大
第4章を考察
グローバル化した中世ヨーロッパは、ラテン語政策で失敗。
英語化された植民地は、分断。
そして現在、過去の失敗を見ずに
「グローバル化!」
「ボーダーレス化!」
を目指してしまっている日本…。
英語化されると、人生の選択肢が減り、「自由」が減ります。
そして英語ができないと給料が増えない、「平等」ではなくなります。
どんどん貧乏になっていって良いのでしょうか。
今日本で起きているのです…。
やめましょう。
私は英語教員ですが、ひしひしと感じます。
うすっぺらコミュニケーション英語教育で日本の英語教育だけでなく、日本語教育や、国民全体が薄っぺらになってしまうことを…。


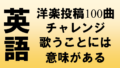
コメント